医学の常識を覆した
脳の“柔らかさ”
テクノロジーで脳の可能性を拓く
神経科学者・牛場潤一 さん
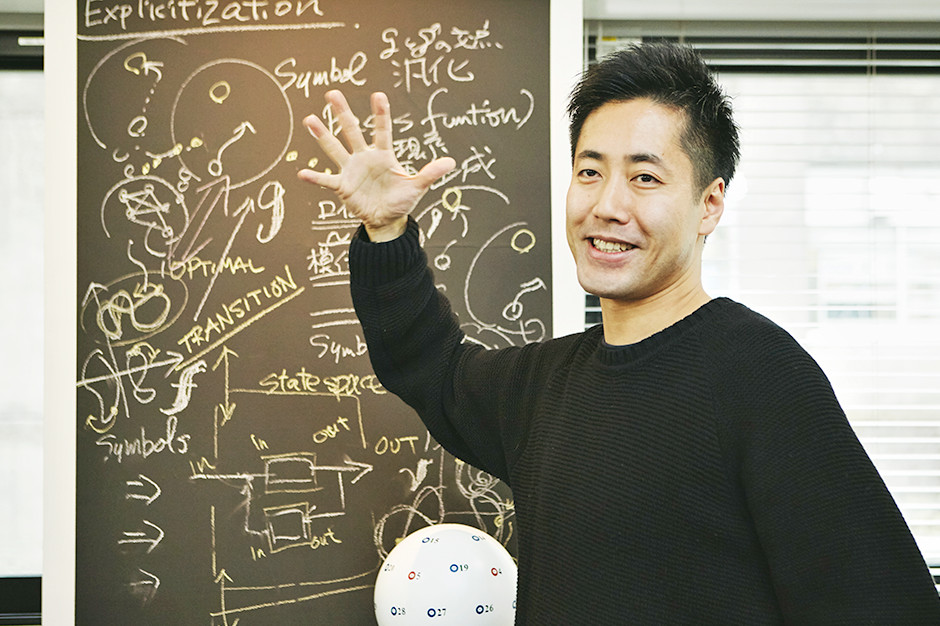
慶應義塾大学理工学部の一室に、クリエイターやアーティストが集っていそうなオープンな雰囲気のラボがある。
部屋の主は、リハビリテーション神経科学研究室とKiPAS人間知性研究室を率いる牛場潤一さんだ。
牛場さんは、脳活動でロボットを動かす「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」研究の第一人者で、BMIを使ったリハビリを考案した。脳卒中で手指に重い麻痺が残った患者にBMIを装着。患者が頭のなかで「指を動かそう」と念じるとマシンが反応して指が動く。これを繰り返すことで、マシンを使わなくても指が動くようになる。
このアイデアは当初、医師に「それは無理でしょう」と爆笑されたという。それでも続けた研究によって、医学の常識は覆された。牛場さんが信じたのは、脳の“柔らかさ”だった。 取材・文:川内イオ/写真:瀧川寛/編集:川村庸子
ラボのなかには「牛バー」
牛場さんの専門は、「理工学部生命情報学科」の「リハビリテーション神経科学」ですよね。白衣が必要な医療施設のような研究室をイメージしていましたが、入り口にバーが!
牛場 ここは「牛バー」なんです(笑)。内装屋さんに入ってもらってつくったんですよ。応接用のテーブルは牛がひく荷台、緑の敷物は芝生をイメージしました。
なぜこの部屋をつくったのかというと、近年世の中が複雑化、高度化して、サイエンスや科学技術が難しくなってきているからなんです。分野が専門的すぎて、隣のラボ(研究室)の人すら僕の論文を読んでないという状況になっている。専門家集団として研究を進めていくなかで、質実剛健さだけでなく、遊び心のあるラウンジのようなラボにすることで、近視眼的になりそうなものを少し解放できると思うんです。
そのために本棚も文化、文明、哲学、アートのような理工学と異なる分野の書籍や雑誌を置いています。リラックスして既存の常識に捉われないかたちで発想するような雰囲気をつくりたかったんです。
サイエンスはどんな人に対しても心を動かすものを提供できるものだと思うし、そうありたい。だから、一般の人に関心を持ってもらえるようにしたいと思っています。
僕、アートが羨ましいなと思っていて。大小さまざまなスケールで街中に美術館やギャラリーがあるじゃないですか。そういう環境があって、デートでアートを見るという文化がある。サイエンスでもそれをやりたいんですよ。
アートがやっているようなリーチの仕方をしたいと思っていて、このラボはその練習の一環でもあります。

驚くべき脳の「柔らかな性質」
牛場さんの狙い通り、「牛バー」の存在で一気に親近感がわいたところで(笑)、どんな研究をしているのか教えてください。
牛場 僕は、脳活動を計測してロボットを動かす「ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)」の研究をしています。BMIは、頭に電流を計測する機器をつけて、脳波に反応が出たら接続している機械が動くというシステムです。
2007年頃から、このシステムを脳卒中のリハビリに活用できないかと考えてきました。脳卒中によって手指がまったく動かせないほど麻痺してしまった患者さんにBMIをつけて「手の指を伸ばす」と念じてもらう。その脳波に反応して、手に装着した機械が動いて指を伸ばします。同時に腕の筋肉にも電気刺激を与えるということを繰り返すことで、脳のなかに残っている神経回路が活性化し、指を動かせるようになるのではないかという仮説です。
研究は、医学部と連携してやらなくてはならないので、最初に慶應義塾大学の医学部の先生に相談したら、「いやいや、それは無理でしょ」と爆笑されました。
当時の医学的な常識では回復不可能で、それを前提に生活支援や就労支援が行われていたんです。でも、僕は「学問的には治らないとは言えない」と思っていた。先生方をしつこく口説いているうちに、少しずつ実験をさせてもらえるようになりました。
そうしたら、ひとり、ふたりと指が動くようになる人が出てきたんです。
いまは治療効果が広く認められるようになったので、BMIを医療機器として世の中に出すべく、パナソニックと製品版を共同開発中なんですよ。慶應義塾大学医学部リハビリテーション科と連携しながら、今年中に4つの病院で治験を始めて、安全性と有効性がデータとして示されれば、医療機器として認可されます。
それはすごい! でも、なぜお医者さんも匙を投げる重度の麻痺から回復することができるのですか?
牛場 脳は本来、「柔らかに機能を書き換える能力」を持っているんです。
例えば、頭に電極を付けて念じることで、パソコンのモニター上に表示される猿のしっぽ「BMIしっぽ」を動かして画面のなかのリンゴを取るという実験をしました。最初は誰もやり方がわからないのですが、試行錯誤しているうちに、3日間ぐらいすると動かせるようになって、そのうち自由に操れるようになる。BMIしっぽが身体化するんです。
つまり、人間はある状況に置かれれば、まったくわけわからないものであっても、自分自身の一部のように取り込んでいく。脳は、そのくらい柔らかな性質を持っているのです。
この性質をうまく引き出せば、脳卒中で麻痺した手も動かせるようになるのですが、さすがに自力では難しい。それなら、テクノロジーを使ってサポートしてあげればいいんじゃないの? ということで、センサーを使って脳の活動状態をモニタリングして、正しいパターンが出たときにだけロボットがアシストしてくれるというのが、このBMI治療です。
「脳が本来持っている力を引き出す」というのが僕らのコンセプトですが、いままでのリハビリ医療の世界では、脳の柔らかさを十分に扱うことができていなかった。文部科学省がBMI研究を支援する動きになったとき、ロボットが動くどころか身体が治りますという話をしたら、これはおもしろい! ということになって研究費がつくようになりました。

子どもの頃の体験がヒントに
どうして、医学界が見過ごしていた脳の柔らかさが持つポテンシャルに気づくことができたんですか?
牛場 小学生のときにコンピューターサークルに入っていたのですが、ある日、人工知能の研究をしている大学院生が自作のプログラムを持ってきてくれたんです。それで謎解きゲームをしていたら、人工知能がどんどん進化していくんですよ!ゾクゾクしました。僕たちの脳も、こういう仕組みで機能がアップデートしていくのかな、と思ったことが「脳」に興味を持ったきっかけです。
その後、中学校で神経科学者の御子柴克彦先生の講演があったのですが、先生がネクタイを外して、ジャケットを脱ぎ捨てて、前のめりで「子猫を縦縞しかない環境で飼育すると、そこから外に出しても横縞は認識できない」という話をしていたんです。
その講演の内容もおもしろかったんですけど、子どもたちに熱弁している先生の姿を見て、おじさんがこんなに熱中できる分野って夢があっておもしろそうだなと思いました(笑)。
それからどんどん「脳」に惹かれて、神経科学者の松本元先生の子ども向け講座にも行きました。そのときは、片側の脳が損傷してしまったのに、残されたもう一つの脳が機能を変えて失った能力を補っているという実在の少女の話をしていて、先生は「それくらい脳は柔らかなんだよ」と言っていたんです。
ふりかえってみると、御子柴先生と松本先生の話はどちらも脳の柔らかさのことを言っているんですよね。脳には限界もあるし、可能性もあるという。ひとつの個体のなかで、良くも悪くもダイナミックに機能が変わりうる、進化も退化もする柔軟な臓器が脳なんだと知ったことが、強烈な印象としてずっと頭のなかに残っていたんです。
醜いアヒルの子の劣等感と反骨心
なるほど! でも、お医者さんに否定されたときに、止めようとは思わなかったんですか?
牛場 実は僕、子どもの頃から文系科目の成績は良かったんですが、数学や物理など理系科目が本当に苦手で、自分でも全然センスないなと思っていたんですよね。
だけど、脳についてはずっと勉強したいと思っていたし、高校生のときに祖父が脳卒中になって苦しんでいるのも見ていたから、脳や工学、医療を学んで、祖父を助けるような技術がつくれたらいいなという思いもあって、理工学部に入ったんです。
でもいざ入学したら、理工学部にはいわゆる「理系オタク」みたいな雰囲気があって、あまりにも自分と感覚が違って馴染めないし、勉強ができる人も多くて、すごく挫折感を抱いていました。
まるで醜いアヒルの子のような気分だったんですが、そのなかでゴリゴリの理系の人が思いもつかないようなアイデアを考えて、それを理系的に解くことで、自分の持ち味が出せるんじゃないか。自分のユニークネスを出せば、この人たちには絶対届かない領域がつくれるだろうっていう反骨心みたいなものもあったんです。
自分で何かをクリエイトしたいという想いが強かった。BMIの研究にしても、学問に素直に従えばBMIで脳が治らないとは断言できないと思っていたので、周りがピンときていないなかでも研究を続けました。
劣等感や苦手意識が強みに変わった、というよりも、自ら変えたんですね。
牛場 僕は、学問的にはコンプレックスの塊でしたからね(笑)。医学や脳のことをやりたくても、自分は医学部じゃないし、師匠は神経科学者でもない。だから、学会でもいつもアウェーで、いつも本流でキラキラしている人たちを見て羨ましいなと思っていました。
でも、いまふりかえってみると、勉強ができたり、良い環境にいることよりも、寝ても覚めても「これって何だろう?」と思えるテーマに出会って、苦労してもいいからやりたいと思えることのほうが重要だと思うんです。それがあれば勉強することが楽しい、わかることが楽しいという状態になりますからね。
それに、何かが得意な人が大多数という環境のなかで、それが苦手だとか、違和感を感じている人はある意味ではすごくチャンスだと思います。その他大勢と視点が異なるので、オセロがばばばばっと一気にひっくり返るようなユニークな発想をしたり、おもしろいものができるかもしれませんから。
文化文明ができるプロセスの解明に挑む
今後はどういう研究を進めていくのですか?
牛場 音楽、スポーツ、伝統芸能などさまざまな分野で、技能性の高いスキルを学習して、それを仲間内や次世代に伝承していくということが行われていますよね。文化遺伝子(ミーム)と呼ばれることもある事象です。
すごく複雑な運動技能の獲得とそれを他者に伝えていくというプロセスがあるわけですが、それがどういう脳の働きで行われているのか、まだ自然科学的に解き明かされていないんです。
僕は、その背後に基本的な原理があるはずだと思って、BMIを使って調べています。先ほど説明した、パソコンのモニターに表示される猿のしっぽを念じて動かす「BMIしっぽ」の実験も、その一環です。この実験で、まったくやり方がわからないような動きでも、継続的に取り組むことで脳が適応して自分ごとにしていく能力があるとわかりました。
こういった適応過程をMRIを使って調べることで、脳のどういう部分がそういった機能を担っているのか、徐々にわかるようになってきています。
これからは、BMIしっぽの実験を複数人で同時にやろうと計画しています。例えば「みんながしっぽをうまく動かして、りんごを取れるようにならない限り実験は終わらない」という設定にして、コミュニケーションがしっぽの動かし方の学習にどのような影響を与えているのかを調べたいんです。
この実験で技能の獲得と伝承のプロセスを解明して、文化や文明ができるプロセスを神経科学的に調べようという試みです。
人間の生物学的な柔らかさを引き出す
人間の脳ってまだ解明されていないことが多いんですね。
牛場 そうですね。これまでの研究では、与えられた課題に対して何日も取り組んだ結果、脳が大きくなると思われていたんです。筋トレによって筋肉が太くなるようなイメージに似ていますね。でも、僕らの研究では、それとは違うおもしろい結果が出ました。
難しい課題をやっている最初の1時間にMRIをとると、被験者の脳の一部の密度が変わるんですが、大きく変わった人はその後の上達の度合いが高く、反対に密度があまり変わらなかった人は、上達の度合いがあまりよくありませんでした。
これは、脳の柔らかさが影響しているのではないか。つまり、最初の1時間の時点で脳の状態が構造的に変わりやすい人は、おそらく脳が柔らかくキャパシティがあるので、学習能力が少し高いのではないかと考えました。
この脳の仕組みは、リハビリにも応用できるかもしれません。患者さんにも、治りやすい人と治りにくい人がいるんですよ。そうであれば、最初に脳の反応性を見て、反応が大きい人は治る可能性が高いから継続する、反応が小さい人は麻痺してない手を積極的に使って生活できるような代替医療に集中したほうが、本人の負担的にもコスト的にもベストだという判断ができるようになるかもしれないなと思います。
柔軟性や吸収力が高い人を「頭が柔らかい」と表しますが、脳の研究でも共通しているとは!
牛場 普段生活していると、脳ってどういうものかなんて考えないでしょう。脳がつくり出す、一人ひとりの人生、集団社会、そして自然との関わり。僕らが何気なく過ごしている日々のなかに、こういうルールや性質があるということが科学の力で露わになると、目からウロコが落ちるような感覚が生まれる。特に意識もしていなかった物事に対して、不思議さ、尊さ、美しさ、畏怖の念を感じるようになる。そんなふうに、科学には世の中を見つめる視点を豊かにしてくれる力があると思うんです。
そういう科学の力をもっともっとクリエイティブに表現して、科学という学問の可能性を拡げたい。
科学を深めることとともに、手が動かないんだったらロボットハンドをつけるというサイボーグのような発想ではなく、人間に残された生物学的な柔らかさを引き出す、そのために寄り添ってくれるテクノロジーも自分の手でつくりたいんです。人に寄り添って、一緒に伴走してくれるテクノロジーが、もっとあっていい。
だから、学問としても、社会への応用としても、エッジの部分をクリエイトして、科学技術という概念を押し拡げることをやっていきたいと思います。
