楽しくて危険な
文学の魅力
感覚や感触から始める読書体験
文学研究者・阿部公彦 さん

わたしたちは現代文の授業を通じ、詩や小説を読んで「作者の意図」や「登場人物の気持ち」を理解するための訓練を積む。それはある種の「正解」を探る読書であり、文学もその延長線上でイメージされる学問だろう。しかし、これとは異なるアプローチを追求している文学研究者がいる。
文学研究者・阿部公彦さんが行っているのは、読んだときに生じる「感覚」や「感触」にフォーカスを当てて作品を論じるというユニークな研究だ。既成のジャンルではなく、「幼さ」「即興性」「凝視」「スローモーション」といった独自のキーワードで文学作品を分析してきた阿部さん。そのお話から見えてきたのは、自由で刺激に満ちた文学本来の魅力だった。
取材・文:清田隆之/写真:Patrick Tsai/編集:川村庸子
村上春樹はなぜ好き嫌いが別れる?
本の読み方というのは、思いのほか国語の勉強に影響を受けているように感じますが、阿部さんはどう思われますか?
阿部 確かに中学や高校の授業では、文学作品にはあらかじめ設定された正解があって、それを正しく捉えるのが読書だという風に習いますよね。もちろん読解力を養う上で大切な訓練だと思いますが、ややもすれば窮屈な読み方になってしまい、それだけでは作品を十分に楽しむことはできません。
実は文学作品って、読み手の接し方次第でいろんな顔を見せてくれるものだと思うんですよ。「情報」を伝えるだけのものではない。誰が何をしたとか、ここがどんな場所だとか、そういった情報は確かに大切なものです。しかし、それよりも重要なものがある。例えば「感触」です。
詩や小説を読んでいると、どうってことのない部分なんだけど、不思議と引き込まれてしまうとか、妙な気持ちになるとか、イライラするとか、すごく幸福な気分になるとか……そういうことがよく起こりますよね。読書というのは、単に書かれてある情報を受け取るだけでなく、読んでいる過程で自分のなかに発生する感覚や感触を味わうことも含めた行為ではないかと考えています。
「感覚」や「感触」にフォーカスを当てる読み方とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
阿部 まずはとにかく、作品と接するなかで自分のなかに湧き起こるものを感じたい。そして、それらが一体どういうものなのか、見過ごさずに捕まえてみる。すると、だんだんそれらの間のつながりや、作品特有のメカニズム、さらには鍵になることばのようなものが浮かびあがってくる。「幼さ」や「即興性」、「凝視」「スローモーション」というのも、そうやって浮上してきたキーワードです。
例えば私は、村上春樹がそれほど得意ではなかったんですね。かと言って全否定する感じでもない。惹かれるところもあるんだけど、言葉にならずに躊躇してしまう部分もあって、この「えも言われぬ感覚」は何なんだろうと、前から気になっていた。それを言葉にして整理してみたのが、拙著『幼さという戦略』(朝日選書)のなかで書いた「村上春樹とカウンセリング」という章です。
村上春樹の小説では、登場人物たちはあらかじめ与えられたキャラクターから逸脱せず、会話も概ね「一対一」で交わされ、その関係も固定化されていて、やりとりする言葉にも奇妙なほどの透明さがある。謎や不可解さはいろいろあるのに、世界の輪郭は不思議と明瞭でブレがないんです。そういうなかで、主人公は「自分に何かを教えてくれる人たち」と関わりを持ち、その対話(=カウンセリング)のなかで救いを得るというパターンが繰り返される。こういう物語を可能にするのは、背後にある「幼い者と賢者の関係」ではないかと考えたわけです。純粋さや透明さへの強いこだわりもそこから説明できる。そこに共感できるかどうかが、村上春樹好きとそうでない人を分けるポイントなのかなと感じました。
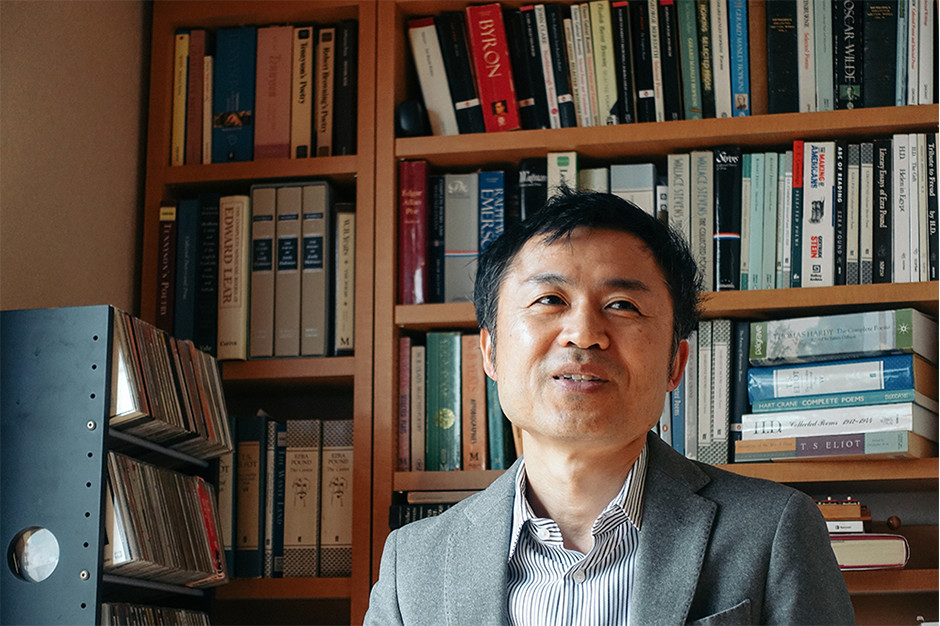
自分なりの“発見感”を楽しむ
なるほど。言わば、「自分のなかに生じた感覚をあとから言葉で追いかけていく」という作業なんですね。
阿部 そうですね。実際に大学でも、学生たちにそういった作業をしてもらっています。まずは作品を読み、おもしろかった部分に線を引いたり、メモを取ったりしながら、気になる感覚や感触を見つけてもらう。それを「なぜこういう風に書かれているのか? その効果は?」という問いに落とし込み、自分なりの答えも用意する。そして授業でほかの学生たちに問いとして投げてもらいます。そうすると大概、本人が用意した答えとは異なる答えが返ってくる。視点の異なる意見に触れると、自分自身の立てた問いの思いがけない奥行きが見えてきたりします。
気になる部分は、本当に何でもいいんですよ。この文章はカタカナが多いのが気になるとか、句読点が多用されることでおかしなリズムが生まれているとか。あるいは、この作者はなぜ「わたし」という言葉を使わないんだろうとか、自分はなぜこの文章を読むとイライラするんだろうとか……。とにかく自分が気になったことから出発する。
もちろん、それによってぐんぐん作品の奥へ進めるような問いもあれば、そうでない問いもあります。アカデミズムの基準に照らせば、やはり「いい問い」というものは存在する。ただ、それが正解というわけではないし、必ずこう読まなければならないというものでもありません。自分なりの視点を持つというのは言うほど簡単なことではないけれど、自分なりの“発見感”みたいなものがないとおもしろくないし、個人個人が「自分にも何か言えることがあるかもしれない」という気持ちで作品に向き合うことが大切だと思っています。
自分の感覚や感触の正体を明らかにするという作業は、読書以外にも役立つような気がします。
阿部 要するに出会いや遭遇の問題なんですよね。文学作品を読むという行為は、連作の場合を除いて、すべてがゼロから始まります。見知らぬ世界で見知らぬ人と出会う。その出会い頭に何が起きているかがおもしろいところだと思うわけです。
多くの場合はプラスの出会いを求めているけれど、場合によっては相性が悪いということもあるし、最初から苦手だなと思う人もいる。でも、未知なるものと遭遇したときに積極的になれるのが人間の強みであり、文学作品を読むのは、それをすごく高い純度で体験することだと言える。
だから人間関係にも、恋愛関係にも、国際関係にも当てはまる。生きる上で「知らないものと出会うこと」に人間はすごいエネルギーを使っているので、出会ったときに人間の心に何が起きているのかを考えていくと、わたしたちが既に知っている概念が別のかたちで意味を持ってくることがあると思っています。
ワインのように文学を表現してみる
そもそもなぜこういった読み方を追求しようと思ったのでしょうか?
阿部 ベースには個人的な読書体験があります。昔から好きになる作家がバラバラで、例えば中学生のときは、五木寛之ばかり読んでいたかと思えば、いきなり志賀直哉にハマったりして、統一感がなかった(笑)。大学生になってからは詩を読むようにもなったんですが、バラバラな読書体験のなかで、ハマる作家、ハマれない作家がいたり、同じ作品でも乗れる瞬間と乗れない瞬間があったりして、それが不思議だなと思っていたんです。
そんなことをずっと考えているうちに、作品が提供してくれるものはこちらの気分によっても変わることがあるし、そもそも書き手や読み手の性格や生理的な問題が重要なファクターになっていることが徐々にわかってきた。それで、思い切って感覚や感触といった生理的な部分そのものを語ったらおもしろいんじゃないかと思って研究を進めたのがきっかけです。
音楽とか、ワインの味とか、「これはまるで○○のようだ」って、みんな普通に感覚を言葉で表現しますよね。そういう評価って個人的なものだし、普遍性もあまりないし、不安定だし、最初はいかがわしいと思っていたんです。「印象」にすぎない。でも、むしろそうした不安定さや変化自体を楽しんだらいいんじゃないかと、前向きに捉えるようになっていきました。
ワインの味みたいに文学作品を表現するって、おもしろい発想ですね(笑)。
阿部 出発点は詩の研究で、博士論文の構想では「叙情とは何か」という大きな枠をつくり、「退屈」というテーマを立てました。叙情性と聞くと何かしっとりとしたセンチメンタルなイメージを抱く人も多いかと思いますが、詩に表現されている叙情にはほんとうにいろいろなものがあります。一般に想定されているような甘い感傷性だけではなく、硬いもの、荒涼としたもの、穏やかなもの、クラクラと目眩がするようなものなど、さまざまな情緒や感触が入ってくる。これらはどのようにして表現されるか。その背後にはどんなメカニズムや思考や生理があるのか。そもそもテキストと読み手の間にはどんな関係があるのか。そういった部分が興味の対象になります。
広く言えば一種の「分析」ですが、感触というのは情報やデータと違って簡単にカテゴリー化できない場合が多いので、分析しにくいものですよね。こういうものをがんばってカテゴリー化していったらおもしろいんじゃないかと。
わたしは数学がものすごく苦手なんですが、カテゴリー化しにくいものと付き合うのはわりと好きなんです。
研究というのは一般的には「全体を貫く普遍的な法則」を目指して進むわけですが、わたしのアプローチでは、どうしても個別性へ向かうことになる。つまり「この作家のこの作品にはこういう感触があった」という方向ですね。だから、例えば本にするときなどはまとめ方が難しくて、タイトルを考えるのにいつも苦労するんですよ(笑)。

文学は本当に「役立たない」学問なの?
『幼さという戦略』では村上春樹のほか、太宰治、武田百合子、多和田葉子、小島信夫といった作家について論じられていました。作家論に触れ、実際にその作品を読んでみたくなったのもおもしろい体験でした。
阿部 そうですね。作品論だけじゃなく、作家論を読むのもおもしろいと思います。批評とは対象を頂点にして一種の「三角関係」を作る行為で、例えばわたしの本を読んでくれた人は、わたしと一緒に村上春樹や太宰治を眺めることになるわけです。当然、視点がずれているので見える物も少し異なるのですが、にもかかわらず対象を共有する。それは心理学で言う「共視」というものに近く、例えばよくお母さんが子どもに対して「ほら、あれを見てごらん」と指をさして同じ光景を見させますよね。このプロセスは母子間の信頼関係を築く際に非常に大切なんだそうですが、批評というのはそういった行為だと思うんです。
異なる視点から微妙にずれたものを見ながら、どうお互いの反応を摺り合わせていくか。難しいけれどおもしろくもある。そのズレから、新しい興味や新しい発想も生まれる。
わたしは文学研究者として、作品からエネルギーをもらいながら、作品がより生きるようなものを書いていきたいと思っています。だから、読者がその作家の作品を読みたくなるのはすごく嬉しいです。
文学ってどこか宗教に近いものが宿ると思うんですよ。例えば村上春樹の小説が100万部売れたとしても、実際に最後まで読む人は100分の1にも満たないはず。例えば冷蔵庫を買ったのに使わないという人はまずいませんが、文学作品は読む前にはその効能がわからず、買っても読まないかもしれない。「読みたい」「知りたい」「お近づきになりたい」という気持ちがそのままかたちをなしたようなもので、言わば買うことそれ自体に意味があるという、不思議な消費財だと思います。むしろお守りに近いのかもしれない。
じゃあ、そんなものは非合理的で無意味なのか。でも、考えてみれば人間の生というのは、そうした必ずしも根拠の定かでない興味や知識欲に支えられているものです。それは究極的には「愛」の力のようなものです。読む方もそうですが、書く方も同じで、そもそも読んでくれないかもしれない不特定多数の読者に向かって何事かを語ろうとする衝動を支えているのは、よくわからない、下手するとあやしくさえある愛の力ではないかと思うのです。読まれなくても仕方ないという気持がないとやれない。
2015年に刊行した『善意と悪意の英文学史―語り手は読者をどのように愛してきたか』という本ではそのあたりのテーマを追求しました。人間を生きさせる根源的な力がどこから湧いてくるのか。宗教が力を失いつつある時代だからこそ、文学作品がどのような磁場を生み出すものか、考えてみる価値はあると思います。
いまは「文学部廃止論」が叫ばれ、文学は役立たないものだと言う人も少なくありませんが、阿部さんはどう感じていますか?
阿部 そういった風潮が強まっていることは事実です。大学教育においては、人文学にも普遍性が求められることが多いんですが、実際にはかなり無理があると感じます。もちろんそのあたり上手に対応している分野もあるし、普遍性やシステマティックな思考方法をいかに表現するかということに人間はずっとエネルギーを費やしてきました。成果も上がった。しかし、人文系の領域は広い意味での個別性も目指すべきだとわたしは考えていて、そこはまだ十分に語られていない気がしています。
個別性にフォーカスをあてる研究は、問題を追及・探求するだけでなく、捉えられたものをオープンにして見えるものにすることに力点があります。つまり、広い意味での「啓蒙」が絡んでくる。この啓蒙性には中学生や高校生に「教える」という側面ももちろんありますが、より一般的に、いままで知らなかった対象と遭遇するとはどういうことか、わかるとはどういうことか、感じるとは、納得するとは何か。あるいは感じない、わからないとはどういうことかといったことも検討材料に入ってくる。
極論すれば、人文系の学問はすべて啓蒙と関わっているのです。わかることや説明することそのものに焦点をあてるという意味で、その思考法そのものが根本的に「啓蒙的」である。だからこそ、実践的な啓蒙活動のなかから新しい知見が生まれることもあるわけです。啓蒙とは押しつけるという意味ではなく、教える人も含め、何かと出会っていくエネルギーを活性化させるということで、それが人文系の学問のスピリットにもなっています。
普遍性に向かうというのは、どちらかと言うとものごとを収めて安心させるものですが、出会いというのは真逆で、ものごとを流動化・不安定化させるものです。だから興奮もするし、ワクワクもするけど、その一方で心配になったり、秩序が崩れたり、場合によっては束の間、悩んだり病んだりするかもしれない。それでもなお、新しいものを見てみたい、触れてみたいと願うのは人間の本能だし、それが生きていく上でポジティブに作用する。
文学は楽しくて危険な学問で、そこに魅力と可能性が宿っている。せっかく授業やテストでいろんな文章に出会えるわけで、自分なりに楽しい読み方を発見してもらえたら嬉しいですね。
