わたしたちは
触覚のことを忘れている!?
「触れる」を楽しく科学する
触覚研究者・仲谷正史 さん

触覚と聞いて、何のことだかわからないという人はいないだろう。触覚とは五感のひとつであり、触れるという方法で外界とつながるためのインターフェースだ。
しかし、それがどういう仕組みで働いているかと問われると、途端に心許なくなる。
例えば視覚は光を、聴覚は音を感じ取るものだが、では触覚は何に反応しているのか。そして、「やわらかい」「冷たい」「ざらざらしている」などの触感は、一体どんな仕組みで生じているのか──。
触覚研究者の仲谷正史さんは、触覚や触感のメカニズム解明に取り組む一方、「テクタイル」というユニットの一員として、様々なテクノロジーを用いて触れることの楽しさを伝える活動を行っている。
そんな仲谷さんに、実はまだあまりわかっていない触覚の世界を案内してもらった。 取材・文:清田隆之/写真:齋藤彰英/編集:川村庸子
数十ミクロンの髪の毛も感知
「触覚」がどういう仕組みのものなのか、改めて考えたことはありませんでした。
仲谷 そうですよね。例えばスマホでこの記事を読んでいる人も、「いまスマホに触れている」ということを意識していないかもしれません。そればかりでなく、着ている服、座っているイス、立っている床など、実はたくさんの触感を感じているはずなのですが、あまりに身近すぎて気づくこともない。触覚とは、そういう感覚ではないかと思います。
では、その触覚はどういう仕組みで働いているのか。ごく単純に言えば、「皮膚の変形」を感じ取るのが触覚です。より正確には、皮膚には圧力や振動、伸縮や滑り具合に反応する数種類の細胞やセンサーが埋め込まれており、それらが組み合わさってひとつの触感が構成されている。いままさに触れているスマホや衣服の触感も、こういった皮膚の変形によって感じ取られているわけです。
しかも、その感度は素足で数十ミクロンの太さしかない髪の毛を踏んでも感知できるほどのレベル。それが全身に分散していて、その面積は約畳1畳分(1.6〜1.8平方メートル)にもなります。視覚や聴覚に比べると、インターフェースとしてかなりの大きさですよね。そう考えると、触覚って結構すごいかもって気がしてきませんか?
確かに。自分にそんなすごいセンサーが備わっていたなんて意識はありませんでした。そもそも、仲谷さんはなぜ触覚に興味を?
仲谷 学生時代は陸上競技部に所属していたというのもあり、もとから身体にまつわる研究に興味があったんです。そのなかで触覚に特化したのはある種の偶然というか、学部の4年次に指導してもらっていたのが触覚研究者の梶本裕之先生(現・電気通信大学准教授)で、先生から与えられた『タッチ』という触覚の教科書がおもしろくてこの道に入ったのがきっかけです。
そこから触覚における錯覚を解析したり、触覚にまつわる不思議な現象を探したりという研究を行っていきました。あとで詳しくお話ししますが、見間違いや聞き間違いがあるように、触覚にも“触り間違い”というものがあるんですよ。そういうおもしろい現象を見つけ、工学や心理学のアプローチを用いて評価・解析していくのが最初の研究でした。
やがて興味の対象は皮膚そのものへと広がりました。皮膚科学の研究手法を援用して「メルケル細胞」という、皮膚が押されたときの圧力や、凸凹などの大まかなかたちを感じ取る細胞の研究に従事。そうやって触感という現象面の研究から入り、皮膚のなかへとミクロレベルの研究に進んでいったというのが触覚研究者としての個人史です。
赤ちゃんはなぜモノを口に入れたがる?
先ほど話に出た触覚における“触り間違い”とは、具体的にどういうものなんでしょうか?
仲谷 有名なのは研究者の間で「ベルベットハンド・イリュージョン」と呼ばれている錯覚で、テニスのガットを両手で挟み、重ね合わせた手でガットの表面をなぞると、なぜかヌルヌルしたベルベット生地のような触感が手のひらに広がります。
こういった「触錯覚」は、これまで50種類以上発見されてきました。ベルベットとテニスのガットは似ても似つかない感触ですよね。それなのに不思議と同じ感触がする。触感とはモノ(素材)のなかに宿っていると考えがちですが、実は触れ方や心のあり方、視覚や聴覚からの情報など、様々な要素が合わさって生成されているものなのです。
また触覚というと直接触れることで得られる感覚をイメージしますが、それだけではありません。例えばテニスのラケットを持っていれば、ラケットを振って届く範囲まで身体感覚が拡張されます。
僕が勤務している慶應義塾大学の湘南藤沢キャンパスには、最寄りの駅から大学まで、車両2台分を連結したダブルデッカー式の送迎バスが走っているんですが、あの長いバスをスムーズに操る運転手は、おそらく先頭から最後尾まで身体感覚が拡張しているはず。車体をどのように感じ取っているのか、いつも想像しながら乗っています(笑)。
なるほど。そう考えると、いわゆる「第六感」というか、嫌な予感がしたときに皮膚がざわっとするのもひとつの触覚なのかもしれませんね。
仲谷 そうですね。第六感なのか内臓感覚なのかわからないですが、知らない人に会ったときや知らない場所に行ったときなど、何かの危険を感じると確かにざわっとしますよね。必ずしも皮膚が応答しているわけではないと思うんですが、身体が誰かや何かに相対することによって持つ自動的な応答みたいなものは、ある種の触覚と言っていいかもしれません。
触覚って、実は五感の中で最も発達が早いんですよ。妊娠10週目のころから自分の身体や子宮壁に触れるという行動が見られ、学習が始まっていると考えられています(視覚も聴覚も反応が始まるのは生後数ヵ月)。赤ちゃんって何でも触れたがりますよね。口の中にモノを入れるのも、味を確かめているわけでなく、唇や舌が鋭敏な触覚器官だからです。
赤ちゃんにとって触ることや舐めることは、見たり聞いたりするより確かな情報を得られる手段なんですよ。我々は誰しも、最初は触覚的な存在だった。
例えばマンガなどで、目の前で起きている現実が夢や幻覚じゃないことを確かめるためにほっぺをつねるシーンをよく見かけますよね? ああいう事例からもわかる通り、触覚は「確かに実在している」という感覚を最も強力に裏づける手段なのです。
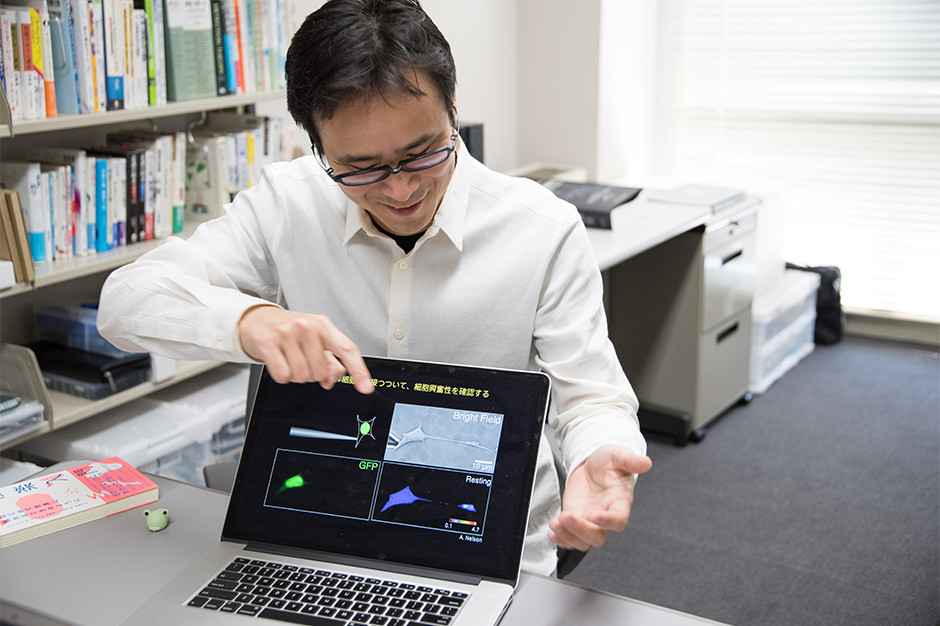
頭と身体がちぐはぐになっている現代
そんな頼りになる触覚の存在を、なぜ我々はつい忘れがちになってしまうのでしょうか?
仲谷 情報がたくさんある環境で、常にすべてのものを触って確かめて生きていくというのって、当然ながらとても大変な作業ですよね(笑)。それに、同じ触感でも人によって感じ方が異なるし、同じ触感を再現することも難しいし、バリエーションも無限に広がっている。触覚や触感というのは極めて個人的な体験のため、一般化しづらいのです。
もちろんそれが触覚の魅力でもあるんですが、コミュニケーションの道具としては、ちょっと曖昧です。逆に言葉はある程度コード化されているというか、意味が共通していて、やり取りがしやすい。我々には時間的にも体力的にも金銭的にもリソースが限られているので、やはり言葉なり視聴覚の情報なり、コミュニケーションしやすいものにシフトしていくのは必然かなとは思います。
ただ、これは『触楽入門』(朝日出版社)という本でも書きましたが、現代はネットやスマホの発達などもあり、情報のほとんどすべてが言語と視聴覚に限定された状態で提供されています。
ネットで記事を読み、SNSでコミュニケーションを取り、スマホで音楽や動画を楽しむ──。これほどまでに文字が読まれ、視聴覚が偏重されている時代は、人間の長い歴史で初めてのことです。その結果、我々は「心身分離」という状況に置かれているのではないかと感じています。
それは具体的にどういうことですか?
仲谷 つまり、身体性を欠いた情報のやり取りを続けるなかで、頭では「つながっている」というメッセージを受け取っているのに、身体は何かが足りないことを皮膚感覚で感じている。心身分離とは、そういう“頭と身体がちぐはぐな状況”を指す言葉ですが、我々は頭で受け取っていることと自分の身体とを、いま一度紐づける必要があるのではないか……。
そこで重要になってくるのが触覚です。もちろん触覚だけで生きていけるわけではないのですが、触覚があることで視聴覚の情報が下支えされるような状況をもう少し見つけていくことができたらいいなと考えています。昔から存在するアイデアではありますが、スマホやパソコン画面を通したコミュニケーションに触感フィードバックがあるだけでも、得られた情報を実感を持って体験することができるかもしれません。
i Phone7でも触感を付加したステッカーを送って、テキストメッセージをより魅力的なものに見せる工夫が採用されています。触覚を再現できる技術がさらに進歩することで、金属のひんやりした触感や、お湯が注がれたときのぬくもり感も伝えられるようになってきている。モバイルデバイスがいわば触感のパレットに変化して、さまざまな体験を再現できるようになりつつあります。
SNSの投稿なんかにしても、視聴覚的には綺麗でも、さらっと流れてしまうというか、スクロールすればすぐに消えていってしまうみたいな感覚がありますよね。それに対して身体で感じた記憶というのは、 “残響”のような後残り感が続きます。 “身体を通したことで残った感覚”のようなものが、触覚が既存のメディアに対して付加できる価値だと考え、研究を進めています。
それ単体だと存在を意識することはないけど、ないとないで何か物足りない。触覚って料理の“出汁”みたいなものなんですかね。
仲谷 そうか、触覚って生きていくための出汁なのか(笑)。確かにそうですね。出汁も飲めばおいしいと思いますが、出されたものがグルタミン酸の味しかしなかったら、やっぱりちょっと残念ですよね。料理の味を下支えするものとして出汁が存在しているように、触覚の上に視覚や聴覚といった情報が乗っかってくると、より深い味わいが楽しめる。そのようなものなのかもしれませんね。
触感を相手に“転送する”装置とは?
我々が触覚に意識的になるためには、どうすればよいのでしょうか。例えば触覚って鍛えられたりするんですか?
仲谷 ひとつは、感じたことを言葉に置き換えていくという方法があります。これは「外化する」という手段で、感覚をいったん身体の外に出すというイメージですね。例えば、大学院の授業の一環で渋谷を歩くワークショップに参加したのですが、その内容は街を歩いているときに自分の身体がどう反応するかを言葉に書き起こしていくというものでした。
これがすごくおもしろくて、自分はどの道を歩きたがっていて、それはなぜなのかと、歩きながら自分を観察していく。そうすると、路面がでこぼこしていたり、削れていたりするところにどうやら自分は惹かれるんだなということがわかってくる。歩くことで環境との対話をし、ふりかえりを通して、触覚への意識がトレーニングされていくように思いました。
これも外化の一種ですが、得た触感や身体感覚にオリジナルの言葉やオノマトペ(擬態語・擬音語)をつくって記録してゆくのも触感への気づきを与えると思います。例えばお医者さんに痛みを伝えるために、ズキズキなのかヒリヒリなのか、感じている痛みに近い言葉を探す作業を誰しもしたことがあるはず。オノマトペをつくるためには感触と音をすり合わせる必要があり、感覚を研ぎ澄ませるためのいいトレーニングになると思います。
人気ドラマ『カルテット』(TBS)でも「みぞみぞする」というオリジナルのオノマトペが話題になっていました。触覚を意識するって、体験学習みたいで何か楽しそうですね。
仲谷 そうですね。触ることに楽しむというのが2007年に立ち上げた「テクタイル」という活動のテーマでもあります。例えば我々がつくった「テクタイル・ツールキット」は、自分が感じている触感を記録して再生できる装置です。ツールキットでつながった2つのコップをふたりに持ってもらい、一方のコップにコーラを注ぐとします。すると、もう一方のコップにもその感触が転送される。空のコップに突如シュワシュワ水が注がれる触感が立ち上がると、みんなびっくりしてくれます。非言語コミュニケーションなので、文字でその驚きを伝えられないのが残念なばかりですが(笑)。
テクノロジーの進化とともに、触感を楽しむコンテンツは今後ますます増えていくでしょう。すでにVR(Virtual Reality)など、バーチャルな体験と触覚を組み合わせたコンテンツが一般化しつつあります。『触楽入門』の中でも触れましたが、未来のオリンピックでは、選手が体感しているラケットの感触がリアルタイムで観客の手に持ったラケットに転送され、身体で試合を体感するといった観戦スタイルが実現するでしょう。
これまでテクノロジーについて述べましたが、難しく考えなくても、誰しも好きな触感はあるはずです。この触感について思い出してみることが、触感を意識するひとつの入り口だと思います。
ちなみに僕は学生時代に大学のすぐ近くにあった洋食屋で食べた蛇腹キュウリの触感が忘れられずに、ときどき自分で試しにつくってみては楽しんでいます。身近な体験ではありますが、日常生活の中でちょっとした触感の記憶をふりかえったり味わったりしてみるだけでも日々の見え方が少し違ってくるはずです。
触覚の記憶は、その人の生きて来た歴史を担保するものとも言えます。個性が宿っていることは間違いないので、ぜひこだわりの、もしくはお気に入りの触感を普段から意識してみると新しい発見があると思います。
